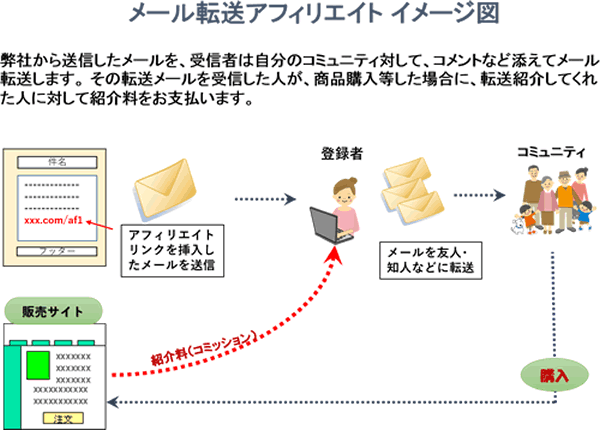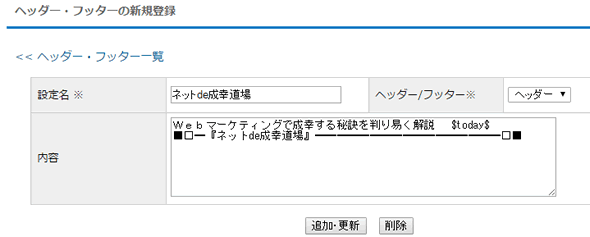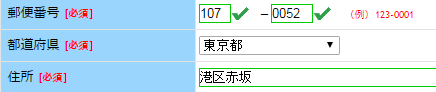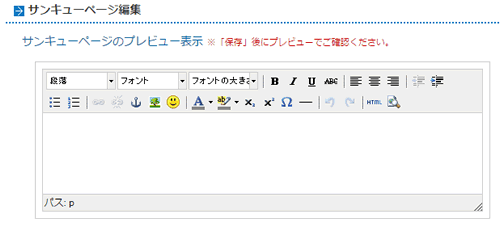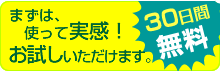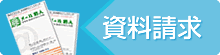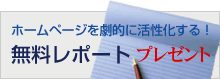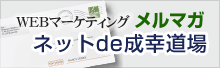クリック率 測定データの見方・使い方
2016-11-24 [記事URL]
 メールマーケティングにおいてクリック測定をすることは基本の一つと言えます。その必要性については、多くの方が理解されていると思います。
メールマーケティングにおいてクリック測定をすることは基本の一つと言えます。その必要性については、多くの方が理解されていると思います。
ですがせっかくシステムを活用してデータを取得しても、充分に活かされていないケースもままあるようです。メール配信時にクリック測定データは、非常に貴重なデータなのに実にもったいないことです。
今回のメール配信講座は「クリック測定データの正しい見方・使い方」について取りあげてみました。
「クリック測定」とは
復習をかねてメール配信システムのクリック測定について、おさらいをしておきましょう。
クリック測定は、人によっては「効果測定」といわれることもあります。
意味あいとしては、メール内に挿入された誘導ページ(以下「ランディングページ」という)の「クリック率」や「クリック数」をシステムを活用して把握することをいいます。
メール配信システムによっては「ランディングページをクリックした人を特定」することを含めた総称としていることもあります。
参考:メール商人の効果測定
クリック測定データの見方・使い方
ここで各クリック測定データの定義について、具体的にしておきましょう。
クリック数 / 何人がランディングページをクリックしたかを示すシステムデータ
クリック率 / 総配信数に対して何%がランディングページをクリックしたかを示すシステムデータ
上の2つのデータの内、特に重要なのが「クリック率」になります。
なぜなら、クリック率はメルマガに書いている内容が「読者の興味対象、読みたいこと」にマッチしているかを知る重要な手がかりになるからです。
同じ対象グループに対して、「Aコンテンツ」と「Bコンテンツ」を書いて配信したときに、どちらのクリック率が高いのかを比較することで、「読者が何を知りたがっているのか、興味を持っているのか」を知ることができます。
逆に「何に興味がないのか」を知ることもできる貴重なデータになります。

メール商人ユーザーから、メルマガに何を書いたらいいか判らない、というご相談を受けることがたまにあります。そういう時は、このクリックデータを参考に読者の興味にそったコンテンツを書くようにアドバイスしています。
仮に「Aコンテンツ」が読者の興味・関心が強いことが判ったら、Aコンテンツを中心にメルマガを構成して、たまに「Bコンテンツ」も織り交ぜるというような工夫が必要です。
クリック測定データを活用する際の注意点
測定データを活用する際に注意して欲しいことが何点かあります。
(1)測定データを他人と比較しない
メルマガライティングのプロフェッショナルのような人が、「平均10%のクリック率を得ている」と自慢気に書いているのを見かけることがあります。
その記事を読んだ人が、「自分は1%にも満たないクリック率しかない。あ~、自分には文章力がないなぁ~ やはりメルマガは私には無理・・」というように否定的にとらえてしまう。
もしくは、「クリック率測定をとっても落ち込むばかり、私の伝えたいことは決まっているのだから、クリック率測定はやめよう・」というような判断をしてしまうケースもあるようです。
こういうような判断は、あまりに短絡的すぎます。
特にクリック測定を始めて間もない方に多いようなので、注意が必要です。
全く同じコンテンツを書いても、配信グループが変わればその反応は大きく変わります。実際に、1桁変わることも珍しくありません。
上の10%といっている人も、実は、すでに関係性のできている特定の配信グループに対して平均10%といっているのかも判りません。
重要なのは、自分と他人のクリック率を比較することではありません。それより、自分が書いたメールコンテンツの違いによるクリック率の違いを見ることです。
その比較を見ることにより、どういうコンテンツであれば興味を持ってもらえるのか・・を知ることが重要です。
設定した配信グループの人達が「なにに興味を持っているのか」 その最大公約数を知るためにクリック率を活用することがポイントになります。
(2) 配信グループによりクリック率は変わる
上の注意点にも書きましたが、同じコンテンツを書いても、設定した配信グループによりクリック率は全く違ったものになります。
クリック率測定によりグループの興味がどこにあるのかを知り「コンテンツをマッチさせる事や、件名の付け方、書き出し方のヒント」などに測定データを活かしていくといいでしょう。
クリック測定データの活用・応用
上にも書きましたが、メール配信システムによっては、このクリック率測定機能で「クリックした人が誰かを特定する」ことができます。(もちろんメール商人もできます(^^)/)
このデータは、使い方によっては、非常にパワフルに活かせます。
例えば、ランディングぺージで何か商品を販売しているケースを想定してみましょう。
メルマガである商品を案内したとします。メール内には、商品を詳しく説明するランディングページへのリンクを挿入しておきます。
そして、そのランディングページをクリックをされたとします。クリックされたということは、読者はその商品に少なからず、興味をもっていると想定できます。
ここで、クリック測定で「クリックした人が誰かを特定」できていれば、「ランディングページをクリックしてはいるが、商品は購入していない読者」つまり有望見込み客をリストグループ化することができます。
このグループリストに対して、後日に「特別条件を提示するとか、キャンペーン情報を告知する」といった濃いアプローチが可能となります。
また、クリックはされているが購入にいたる率が極端に低ければ「ランディングページの作りが適切でない」であるとか、「メルマガのコンテンツにランディングページがマッチしていない」といったようなことがわかってきます。
こういったデータは、前に本講座で書いた「ボトルネックの改善」の重要な手がかりにもなるわけです。
参考ページ:ボトルネックを改善しよう!
クリック測定したシステムデータを参考に、読者の興味にそったコンテンツ作成を心掛けてもらえたらと思います。
それでは今回はここまでとさせていただきます。
また、次回の講座でお合いしましょう(^^)/
執筆: 神田良治 メルマガ「ネットde成幸道場」


 メールマーケティングにおいて
メールマーケティングにおいて